特徴がないのが特徴と言われる美濃焼は、岐阜県美濃地方で生産される陶磁器です。
生活で欠かせない食洗器や電子レンジでも使え、実用性もおしゃれも叶えられる現代生活の強い味方。
100均でも見かける美濃焼ですが、実はよく知らないという方も多いのではないでしょうか。
そこで、今回は美濃焼の魅力をまとめてご紹介します。
この記事を通して美濃焼のすばらしさに触れ、日々の暮らしに美濃焼を取り入れるきっかけになれたら嬉しいです。
美濃焼の特徴とは
美濃焼は「特徴がないのが特徴」と言われています。
しかし、マイナスなイメージになりかねない「特徴がない」ことが美濃焼の強みなのです。
特別な様式がないからこそ、時代に合わせたデザインや表現ができ、新しい様式を取り入れても違和感がありません。和食器だけでなく洋食器にも広く使われ、どんな要望にも応える懐の深さで使い勝手の良い食器が続々と生まれています。
現在、国内における美濃焼のシェアは50%以上。おうちの食器にも、知らない間に美濃焼が隠れているかもしれませんね。
▼ろくろを使った美濃焼の製造工程を3分で解説しています
美濃焼が安いのはなぜ?
100円ショップでも見かけるほど美濃焼が安い理由は、以下の2つが考えられます。
- 大量注文と大量生産で低価格が可能
- 国内で有名な焼き物の産地より生産エリアが広い
たくさん受注してたくさん生産することは、低価格を実現する上で大切なことです。
その大量生産を可能にしているのが、美濃焼生産エリアの広さ。生産地が広ければ、それだけ大量注文を受けられるだけの器が大きくなります。
大量注文と大量生産を受けられる生産地の広さで美濃焼を安く提供でき、身近な焼き物になりました。
織部焼との違いは?
美濃焼と織部焼の違いはカテゴリーです。
美濃焼は特徴がないと前述しましたが、その様式や色などから種類分けがされており、織部焼もその1つ。織部焼には以下のような特徴があります。
- 深い緑色
- 独特な形と豪快なデザイン
いびつな形状や市松模様といった大胆な文様など、自由で個性的なデザインが特徴の織部焼。わかりやすい違いは色ですが、緑だけでなく黒や白の織部焼もあり、見分けが難しい焼き物です。
千利休の弟子である「古田織部」好みであることから織部の名がつけられました。つまり織部好みであれば、織部と同じく美濃焼の1種である志野焼や黄瀬戸、瀬戸黒も「織部」と言えます。
織部が好んだ左右非対称のバランスやゆがんだ形は、特に桃山時代に作られた織部の特徴。形状で見分けるのも1つのポイントです。
瀬戸焼との違いは?

引用元:愛知県陶磁美術館公式サイト
美濃焼と瀬戸焼の違いは産地です。
瀬戸焼の産地は愛知県瀬戸市。実は岐阜県と愛知県の県境を挟んで、美濃焼の産地と隣接した地域なのです。
陶器と磁器両方生産されていることや、土も同じものを使っていることから、明確な違いはありません。15世紀頃には、瀬戸と同様の器が焼かれていたこともあります。
美濃焼の種類にも「黄瀬戸」や「瀬戸黒」があることからも、同じルーツであると言えるでしょう。
もし同じ県内であれば、同じ焼き物として認識されていたかもしれませんね。
多治見焼との違いは?
美濃焼と多治見焼の違いは産地です。
多治見は、美濃焼の産地の1つ。多治見焼は、特に多治見市で作られた焼き物なので、美濃焼の1つと言えるでしょう。
美濃焼の歴史は?

引用元:秀峰窯公式サイト
1300年以上ある美濃焼の歴史を簡単にまとめました。
- 古墳時代から奈良時代の間にはすでに焼き物を生産
- 美濃の最盛期は安土桃山時代
- 江戸時代からの生産は生活雑器が中心
- 明治時代、絵画的な表現の磁器がパリ万博で表彰を受ける
美濃焼を語るうえで欠かせないのが茶の湯です。
安土桃山時代、美濃焼は織田信長の産業振興で発展し、茶の湯の流行とともに芸術性を高めていきました。中国の模倣を離れ、日本独自の「茶陶」という焼き物の世界を作り出します。この時代に作られた茶人好みの焼き物は、今も人気の高い名陶ばかりです。
しかし、一気に勢いに乗ると、わずか40年にも満たない間に衰退してしまいます。
その後、生産の中心を生活雑器に移し、美濃焼は焼き物ならどんな種類でも焼いてしまうと言われるほど、実用性と芸術性両方をかねそなえた陶磁器へと発展しました。
美濃焼はどこの焼き物?
美濃焼の主な産地は、岐阜県土岐市、多治見市、瑞浪市、可児市です。
岐阜県の南東部、愛知県との県境に位置し、美濃地方の東部であるため「東農」地方と呼ばれています。
▼自治体が共同作成した美濃焼の動画です
美濃焼の種類は?
現在伝統工芸品に指定されている美濃焼は以下の15種類です。
| 種類 | 特徴 |
|---|---|
| 志野 | 不透明な乳白色が特徴 釉薬の下に絵付けが施されている |
| 織部 | 落ち着きのある深い緑色が有名(青織部) 黒など別の色もあり 名前の由来は茶人「古田織部」好みであること |
| 黄瀬戸 | 朽葉色と言われる温かみのある柔らかい黄色が特徴 植物の文様が多く見られる |
| 瀬戸黒 | 柔らかさを感じさせる漆黒が特徴 鉄釉を施し、熱いうちに急冷させて黒色にする 文様などの装飾はなし |
| 灰釉(はいゆう) | 草木の灰を溶かした釉が使われた焼き物 |
| 染付 | 白地に青の線で絵を描き、透明の釉をかけた焼き物 |
| 天目(てんもく) | 一般に口が開き高台の締まった形状の茶碗 鉄褐色の釉をかける |
| 赤絵 | 白地に赤色を主に、多彩な絵具で上絵付した焼き物 |
| 青磁 | 淡い青色、青色の釉薬をかけて高い火力で焼いた焼き物 |
| 鉄釉(てつゆう) | 植物の灰に酸化鉄を加えた釉薬が使われた焼き物 |
| 粉引(こびき) | 鉄分の多い褐色に白い化粧土を施し、透明の釉をかけた焼き物 |
| 御深井(おふけ) | 釉薬の鉄分により淡い緑色に発色した焼き物 青磁を感じさせる |
| 飴釉(あめゆう) | 主成分が鉄分の釉薬を使用し、あめ色に発色した焼き物 |
| 美濃伊賀 | 伊賀風の焼き物 |
| 美濃唐津 | 織部の窯で焼かれた唐津風の焼き物 別名「唐津織部」 |
様式による違いは、色や質感などの特徴。
志野、織部は色や技法の違いからさらに種類分けされていますが、その見分け方は奥が深く、一般には難しいとされています。
美濃焼の値段
美濃焼の値段は、作成時期や作家によって変わります。
高額で取引される美濃焼は、作成時期が古くて短い「織部」や「志野」です。安土桃山時代に作られた名陶は、今でも人気が絶えません。
現在活躍している作家の中でも、人気作家や人間国宝の作品は値段が高い傾向が見られます。
前述したように、美濃焼は100均でも取り扱いがあるほど身近な焼き物。工場でも大量生産されており、私たちが気兼ねなく使える「普段使いの器」です。
美濃焼の窯元【一覧】
美濃焼で有名な窯元を特徴とともに一覧にまとめました。
窯元によって特徴が違いますので、ぜひ器を探す際の参考にしてください。
▼窯名をクリックすると公式サイトへ移動できます
| 窯名 | 特徴 | 住所 |
|---|---|---|
| 壽泉窯 | 花のような模様を作る結晶釉が特徴の窯元 家族経営の小さな会社だからこそこだわりの焼き物を製作 |
岐阜県多治見市喜多町4-65-5 |
| カネコ小兵製陶所 | 創業100年を迎えた窯元 シンプルで上品な器が人気 |
岐阜県土岐市下石町292-1 |
| 秀峰窯 | 伝統的でありながらモダンな美濃焼が特徴の窯元 特に美濃焼が印象的 |
岐阜県土岐市駄知町1781-2 |
| 不動窯 | 伝統を大切にしながら現代になじむ器を作る窯元 いつもの暮らしを少しグレードアップできる器が揃う |
岐阜県土岐市駄知町2457 |
| 正陶苑・祐山窯 | 素材感を大切にした、温かみのある器が特徴の窯元 1代目は正陶苑、2代目は祐山窯で活動 |
岐阜県土岐市駄知町387−3 |
| 知山窯 | 赤絵とトルコ青が印象的な窯元 楽器や音符など音楽をモチーフにした商品を製作 |
岐阜県土岐市下石町1476-3 |
| 伸光窯 | 創業130年以上の窯元 生活スタイルに合った機能性・デザイン性の高い作品を作る |
岐阜県土岐市泉町定林寺629-2 |
| 小田陶器 | 白磁の器を100年以上作り続ける窯元 リサイクル食器である「Re50」を生産 |
岐阜県瑞浪市西小田町2-100 |
| ふくべ窯 | 昭和初期に美濃地方で生まれた精炻器を夫婦で製作 鳥や花をモチーフにした繊細な絵付が特徴 |
岐阜県土岐市 |
美濃焼でおしゃれな窯元といえば?

引用元:公式サイト
美濃焼でおすすめのおしゃれな窯元は「SAKUZAN(作山)」です。
毎日の暮らしになじむ、使い心地の良い美しい器を製作しています。
特徴ごとにシリーズ化されており、特に「SAKUZEN DAYSシリーズ」はカラーバリエーションが豊富。食卓に彩りが加わり、毎日の食事が明るく楽しくなりそうです。
| 住所 | 岐阜県土岐市駄知町1369-3 |
|---|---|
| 電話番号 | 0572-59-8053 |
| 営業時間 | 10:00~17:00 ※定休日:土日祝日、年末年始 |
| 口コミ | SAKUZANのGoogleマップはこちら |
| 公式サイト | https://www.sakuzan.co.jp/ |
美濃焼の作家【一覧】
美濃焼で人気作家から、注目の若手作家まで6人をご紹介します。
通販サイトで名前を検索すると作品が見られますので、ぜひ気になる方の作品を目で見て確かめてください。
| 作家名 | 窯名 | 住所 |
|---|---|---|
| 中垣連次 | 秀峰窯 | 岐阜県土岐市駄知町1781-2 |
| 和田一人 | 芳州窯 | 岐阜県土岐市駄知町1809 |
| 加藤芳平 | 松泉窯 | 岐阜県土岐市下石町649 |
| 伊藤豊 | (独立) | 岐阜県瑞浪市 |
| 平野日奈子 | (独立) | 岐阜県多治見市 |
| 田中志保 | (独立) | 岐阜県土岐市 |
美濃焼作家で人間国宝なのは?
美濃焼で重要無形文化財の保持者に認定された人間国宝は6人です。
それぞれ保持している重要無形文化財も異なりますので、表にまとめました。
| 作家名 | 重要文化財 |
|---|---|
| 荒川 豊蔵 | 志野・瀬戸黒 |
| 加藤 土師萌 | 色絵磁器 |
| 塚本 快示 | 白磁・青白磁 |
| 鈴木 藏 | 志野 |
| 加藤 卓男 | 三彩 |
| 加藤 孝造 | 瀬戸黒 |
※2022年9月現在、荒川豊蔵氏、加藤土師萌氏、塚本快示氏、加藤 卓男氏はお亡くなりになっています。
美濃焼のお店で有名なのは?
種類が多い美濃焼は選ぶ楽しみがある一方で、好みの器を探すのが大変と感じる方もいるかもしれません。
そんなときにおすすめのが、美濃焼の器を数多く取り揃える「美濃焼スクエア」です。
美濃焼スクエア

引用元:公式サイト
美濃焼スクエアは、多治見美濃焼卸センター協同組合の直営店です。美濃焼卸センター内にある約20社の陶磁器商社から厳選された器を販売しています。
日常使いから、贈答用まで幅広く取り扱っており、中でもアウトレットは掘り出し物が見つかると人気。
丁寧に説明してくれるスタッフに相談しながら、お気に入りの器を探すのにおすすめです。
- 品質の高い美濃焼をリーズナブルに購入可能
- 「たじみ茶碗まつり」は毎年10月に開催
- 地元陶芸作家の作品も並ぶ
| 住所 | 岐阜県多治見市旭ケ丘10-6-33 |
|---|---|
| 電話番号 | 0572-27-2889 |
| 営業時間 | 10:00~17:00 ※年末年始はお休み |
| 口コミ | 美濃焼スクエアのGoogleマップはこちら |
| 公式サイト | http://www.chuokai-gifu.or.jp/ |
美濃焼の体験ができるのは?
美濃焼に触れ、知ることで実際に体験してみたいと思う方も多いはず。
そこで、美濃焼の体験ができるおすすめの窯元をご紹介します。
角山製陶所

引用元:公式サイト
岐阜県土岐市で、昔ながらの方法で1つ1つ丁寧に美濃焼を製作している窯元です。
絵付体験だけでなく、電動ろくろを使った陶芸体験も行っています。初めての方でもお子さんでも、作り方のポイントを教えてもらえるので楽しく作陶体験ができると人気です。
- 陶芸教室では好きなものが2つ作れる
- スタッフの方が丁寧に教えてくれるという口コミあり
- 天日干ししている製品が中庭に並ぶ様子を見ながら体験できる
| 予算 | 絵付け体験:1,000円+送料 陶芸体験:3,500円(2作品) |
|---|---|
| 取り扱いメニュー | お皿、茶碗、湯呑みなど |
| 特記事項 | 電話で要予約、絵付は1人~、陶芸は2人~ 団体での利用も可能、駐車場有 ▼仕上がりまで 絵付け:2週間程度、陶芸:1か月程度 |
| 住所 | 岐阜県土岐市泉明治町5-1 |
|---|---|
| 電話番号 | 0572-55-2886 |
| 営業時間 | 8:00~18:00 |
| 口コミ | 角山製陶所のGoogleマップはこちら |
| 公式サイト | https://kakuyama.jimdofree.com/ |
美濃焼に関する【Q&A】
美濃焼で気になる疑問を2つご紹介します。
美濃焼は食洗機で洗える?
美濃焼は食洗器で洗えます。
繰り返し食洗器で洗っても欠けたりひび割れたりしなかったという声があるほど、美濃焼は丈夫で硬い焼き物。使用する際は、器同士がぶつからないように工夫する配慮は必要です。
しかし、美濃焼の中には食洗器不可のものもあるので、使用前に必ず確認しましょう。
美濃焼は電子レンジOK?
美濃焼は電子レンジでも使えます。
ただし、電子レンジOKの器でも水分を多く含んだ状態での使用は避けましょう。膨張して器自体を痛めてしまう可能性が高く、頻繁に電子レンジで加熱するうちにいきなり割れることもあります。
電子レンジNGである場合が多い金銀の絵付があっても、電子レンジ対応のものもあるので、必ず使用前に注意事項を確認して使用しましょう。
美濃焼の特徴まとめ

引用元:カネコ小兵製陶所公式サイト
特徴がないのが特徴と言われる美濃焼をご紹介しました。
- 特徴がないのが特徴と言われる
- 1300年以上の歴史がある
- 茶の湯の流行とともに発展
- 現在全国シェアの50%以上を誇る
実用性と機能性、さらにはおしゃれも兼ね備えた美濃焼は、毎日の食卓に彩りを加えながら普段使いもできる伝統工芸品。産地の岐阜県では、伝統を大切にしながらも時代に合った新しい美濃焼を焼き続けています。
美濃焼でお気に入りの食器を見つけて、日々の生活をグレードアップしてみませんか?

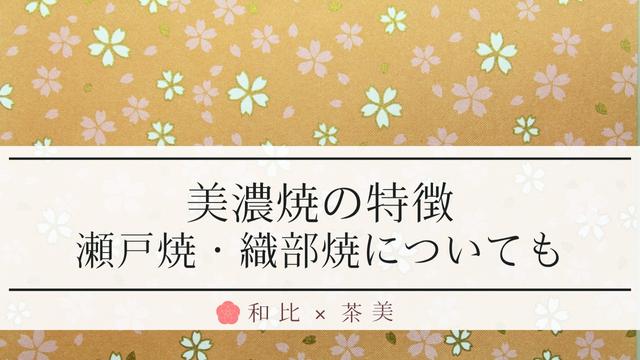
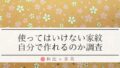
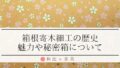
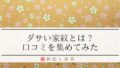
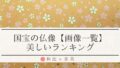
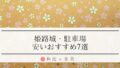
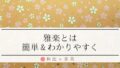
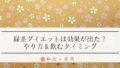
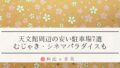
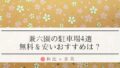
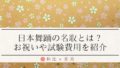
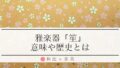
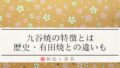

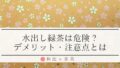
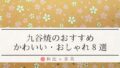
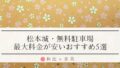
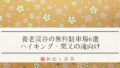
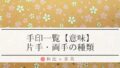











コメント