茶花と聞かれてちゃんと答えられる方はいらっしゃいますか?華道と勘違いしてる方も多いのではないのでしょうか。
初心者のうちは花を扱うことや名前を覚える機会は少ないですが、自分でお茶会を催す立場になったら茶花の知識や技術は必須になります。
そんな時きちんと茶花について理解していないと、後から大恥をかいたりせっかくの花を綺麗に飾れない…なんてこともあります。
そこで今回は茶花の飾り方や季節の花について紹介します。
それではまず、茶花の基本的なことから学んできましょう。
茶花とは?読み方&意味まとめ
茶花の読み方は「ちゃばな」です。
お茶会の席において、床の間に飾られる花のことを指します。
一見すると「ちゃか」と読んでしまう方も多いですが、漢字をそのまま読んでください。(ちなみに中国語で茶花というと「椿」になります。)
茶席ではさまざまな茶花が飾られますが、特に用いられるのが「椿」です。
椿イコール茶花の概念そのもの、と言えるので面白い発見ですよね。
茶花のルールとは?
茶花には色々なルールや作法がありますが、ここでは大前提となるものを紹介します。
似て非なるものに「華道」があります。
侘び寂びという点では同じ文化ですが、華道は花の主張を重視するのに対して茶花はあくまでも「茶席に添えられた花」になります。
華道は花だけでなく、器の派手さも競うことがあります。
現代的な流派は洋花を使うこともあり、立体的かつメートル単位での大きさにもなります。
いっぽうで茶花は「飾らない」ことを良しとします。
自然に生えている山草花を使って、ナチュラルな形に仕上げます。
利休七則(りきゅうしちそく)という、千利休の茶道に対する心構えをあらわしたものにも
「花は野にあるように生け」
とあり花器もシンプルなものを使い、剣山なども使わずにそのまま生けます。
茶花の生け方を解説
実際に茶花を生けるときは、どのようなスタイルにするか紹介します。
自生する草花をつかう
まず材料となる花ですが、なるべく自生するものを使いましょう。
茶道は禅の思想が基盤となっています。
花に限らず道具や茶懐石も含めて、今あるもので最上のもてなしをするのが基本です。
野山に行ける環境にないときには、自宅にある花を使っても問題ありません。
このように茶花が植えられている場所を「茶庭」(ちゃにわ)と呼びます。
都市部に住んでいる方であれば、茶花を専門に扱う花屋さんに相談してみましょう。
季節感を重視する
茶花において季節感は必須です。
いくらその花が綺麗であっても、季節感を無視してはいけません。
農業が発達したことにより季節に合わない花も手に入りますが、基本的にはその季節の花を使いましょう。
ただもてなす相手の好みに合わせたり、お茶会のテーマを優先させるときには例外もあります。
とはいえこれも高等テクニックですので、最初の段階であれば季節の花を使うことをおすすめします。
茶室の雰囲気と調和させる
茶花でいちばん難しいのが、茶室の雰囲気と調和させることです。
花を生ける花器はもちろん、掛け軸や用いる道具との組み合わせも重要です。
これはもてなす亭主のセンスが試されるため、明確なルールがありません。
あえて色や雰囲気を統一させる場合もあれば、バラバラにすることもあります。
とにかくシンプルに
最後に重要なのが、とにかくシンプルにすることです。
茶花には作法や型がありますが、生ける人それぞれによって個性が出てくるものです。
美しい茶花を生けるには多くの教養と知識を身につけ、何度も花に触れることで技術が磨かれていきます。
茶花を生けていて不安になったり、分からなくなることも多いでしょう。
そのときは「シンプルに、野にあるように生ける」という考え方を持ってください。
おすすめは茶花が完成したあと、一度目線を離して引きの視点で茶花を眺めることです。
そのときに全体の調和や、花の美しさについて理解が深まるでしょう。
基本的なことはここで紹介しましたが、いちばん重要なのは実践することです。
教本にも茶花の生け方は紹介されていますが、写真を観察するのと実際に手を動かすのでは全く異なります。
茶花専用のカルチャーセンターもあるくらいなので、茶花はそれだけ奥が深いものです。
詳しいことは各教室の先生に教えてもらいましょう。
茶花の季節の考え方とは?
そもそも、なぜ茶室に花を飾るのでしょうか?
それは茶席が華やかになることはもちろん、季節感を明確にするためです。
掛け軸、炉と風炉の季節、相手にかける言葉などで季節感をあらわすことはできますが実際の季節感を表現するのに、本物の自然には敵いません。
人工的な茶室に唯一生命があるのが「茶花」です。
茶室のなかで最も春夏秋冬を感じられるのが「茶花」でもあります。
茶花の種類【月別一覧】
それではここで、季節ごとの花について紹介していきます。
どんな花を飾るかによって、お茶席の雰囲気が大きく変わるので覚えておきましょう。
1月の茶花
| 蝋梅 | 蝋細工のような美しさがあります。 華やかさは少ないですが、落ち着いた印象になります。茶花としてよく使われます。 |
|---|---|
| 水仙 | 育てるのに手間がかかりません。 凛とした印象があります。 |
2月の茶花
| 蕗のとう | 山菜として楽しむ方もいらっしゃいます。 印象的な香りがあります。 |
|---|---|
| 青文字 | 青文字 丸くてかわいい花です。 一つのつぼみに複数の花が咲きます。 茶花としてよく使われます。 |
3月の茶花
| まんさく | 細長くて黄色い花です。 春になったらすぐ咲くことから「まず咲く」という語源があります。 青文字 丸くてかわいい花です。 茶花としてよく使われます。 |
|---|---|
| 紫花菜 | 道ばたなどの、日当たりの良い場所を好んで咲きます。 葉と花ともに食べることができ、日本には現代になってから入ってきました。 |
4月の茶花
| 木瓜 | 朱色や白色など、中国の陶器にも描かれています。 果実酒にも使われます。 茶花としてよく使われます。 |
|---|---|
| 山吹 | 山吹色という言葉があるくらい、鮮やかな色の花です。 斜面に対して花を下げて咲きます。 茶花としてよく使われます。 |
5月の茶花
| 都忘れ | 水はけの良い場所を好みます。 花言葉には「別れ」という意味があります。 |
|---|---|
| 利休梅 | 清楚な白色の花です。 公園でもよく見ることができます。 茶花としてよく使われます。 |
6月の茶花
| 鳴子ゆり | ラッパのような形の花です。 海岸に咲くことがあります。 |
|---|---|
| 二人静 | 白くて小さい花が一列に咲きます。 同じ種類に一人静という花もあります。 |
7月の茶花
| 露草 | 爽やかな青色の花です。 茎は食べられます。 茶花としてよく使われます。 |
|---|---|
| 利休草 | 花屋ではあまり見られません。 洋風のフラワーアレジメントにも使われます。 茶花としてよく使われます。 |
8月の茶花
| 蕗のとう | 水の中に多い印象ですが、茶室にも飾れます。 日本産は小さいです。 |
|---|---|
| 青文字 | ホトトギス 日本では太平洋側に見られます。 水はけのよいところを好みます。 茶花としてよく使われます。 |
9月の茶花
| 水引 | ご祝儀に使う水引きに似ています。 花はカギがあり衣服に着きやすいです。 茶花としてよく使われます。 |
|---|---|
| ルリヤナギ | 涼しげな印象の花です。 紫色の上品な色の花が咲きます。 |
10月の茶花
| りんどう | 山奥に咲いてます。 消化器官に効能があります。 茶花としてよく使われます。 |
|---|---|
| 石蕗 | 鮮やかなレモン色の花です。 天ぷらで食べることもできます。 茶花としてよく使われます。 |
11月の茶花
| 白侘助 | 椿と並んで茶花に使われることの多い花です。 花びらは柔らかい印象です。 茶花としてよく使われます。 |
|---|---|
| 山法師紅葉 | 花だけでなく、ツヤのある葉っぱも魅力的です。 栽培するとかみきり虫が着くこともあります。 |
12月の茶花
| 南天 | 雪の上に咲くと赤色が映えます。 料理の色付けにも使われます。 茶花としてよく使われます。 |
|---|---|
| 大神楽 | 大きくしっかりとした印象の花です。 枝も太くカーネーションに似ています。 |
▼12月の茶花についてです
茶花の禁花とは?
茶花は基本的にルールがありませんが、使ってはいけない「禁花」も存在します。
流派によってそれぞれ異なりますが、基本的な茶花を説明します。
- 香りの強い花
- とげ・毒のある種類
- 和歌で禁花として詠まれているもの
- 派手なもの
- 名前が上品でないもの
流派によっては、禁花ではない場合もあります。
疑問に思ったら直接先生に尋ねてみましょう。
茶花で枝ものはある?
茶花には花びらや葉っぱだけでなく、枝も使うことができます。
メインになることはありませんが、枝ものを使うことで一気に趣のある雰囲気を作ることができて、何より力強さや個性を表現できます。
また枝だけを考えても、蕾(つぼみ)が付いているものと付いてないものもあります。
主役となる花に合わせて、どんな枝を合わせるとベストか悩みながら生けるのが茶花の醍醐味でもあります。
基本的には枝ものを生けるときは自由に飾りますが、基本的なルールを紹介します。
- 枝は高く飾る
- 全体の後ろに飾る
- 正面は花が美しくなる角度
- 枝の高さは花入の1.5〜2倍
とはいえ「自由に生ける」のがいちばん難しいです。
茶室全体の道具やお客様の好みなどと調和させながら、枝ものが必要かどうかを考えながら使うようにしましょう。
まとめ
茶花は茶室のなかで、ゆいいつ生きているものです。
雰囲気を美しくするために飾るという意味のほかに「いのちや自然に対する感謝」という意味合いも強くあります。
これは茶花だけでなく、華道にも同じことがいえます。
京都の方は現代になっても茶会や華展だけでなく、日常的に玄関や床の間に花を生ける習慣を残しています。
花や自然に対する畏怖の感情や祈りというものが、侘び寂びという禅の思想と融合して日本独自の花文化を形成しました。
ここが海外のフラワーアレジメントと大きく異なる点です。
茶室だけでなく日常的にも、花と触れ合う機会を増やしてみませんか?

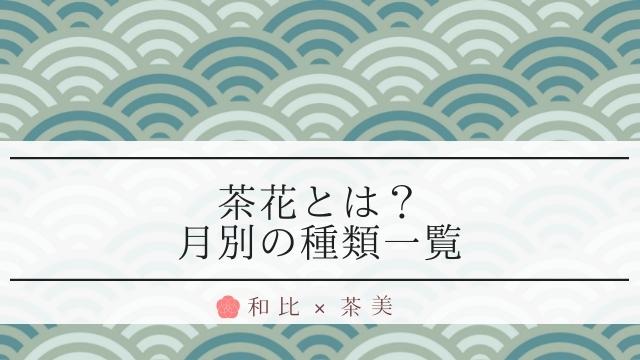

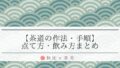

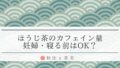


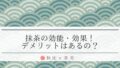

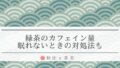
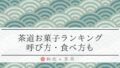







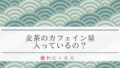

















コメント