ひらひらと舞う姿が美しい蝶。
一年を通して見られる生物であるため、いつの季語なのかわからないという方もいるのではないでしょうか。
今回は季語「蝶」にはどんな子季語・関連季語があるのか紹介します。
蝶の季語はいつ?
| 子季語 | 蝶々・胡蝶・蝶生まる春の蝶・眠る蝶・狂う蝶 舞う蝶・小灰蝶・胡蝶の夢・岐阜蝶 だんだら蝶・双蝶 |
|---|---|
| 関連季語 | 揚羽蝶・夏の蝶・秋の蝶・冬の蝶・凍蝶・芋虫・蛾 |
| 時期 | 三春(陰暦1月~3月) |
| 解説 | 鱗翅(りんし)目の昆虫の総称。 鱗粉でおおわれる四枚の羽で花から 花へ飛び回り、餌の蜜を吸う。 美しい色彩の模様の種が多い。 |
蝶の子季語・関連季語を解説
色鮮やかな色を纏って可憐に舞い、情景に彩りを与える蝶。
子季語・関連季語にはは蝶のいろんな表情を表した語が多く見られます。
| 子季語 | 解説 |
|---|---|
| 蝶々 | 蝶のくだけた呼び名。 |
| 胡蝶 (こちょう) |
蝶の別称。 |
| 蝶生まる (ちょううまる) |
まだ寒い早春に羽化した蝶。 |
| 春の蝶 | 春に舞う蝶。 |
| 眠る蝶 | 花や草にとまる姿を眠ると表した語。 |
| 狂う蝶 | 蝶がひらひらと飛び回る姿のこと。 |
| 舞う蝶 | 飛び回っている蝶。 |
| 小灰蝶 (しじみちょう) |
蝶の一種。 しじみの殻に似た柄をしている。 |
| 岐阜蝶 だんだら蝶 |
明治初期に岐阜で発見された蝶。 |
| 双蝶 | 2匹の蝶。 |
| 胡蝶の夢 | 荘子が夢で胡蝶になり、あまりの楽しさに 自分と胡蝶の区別がつかなくなった という故事から生まれた語。 現実と夢の区別がつかないことを指す。 |
| 関連季語 | 解説 |
|---|---|
| 揚羽蝶 | 蝶の一種。 黄色に黒いすじの入った美しい柄が特徴。 |
| 夏の蝶 | 夏に見かける蝶。 アゲハチョウやタテハチョウなど。 |
| 秋の蝶 | 秋に見かける蝶。 キタテハやウラナミシジミなど。 |
| 冬の蝶 | 冬に見かける蝶。 ウラギンシジミ・ルリタテハなど。 |
| 凍蝶 (いてちょう) |
寒さによって凍てついたように 動かない蝶のこと。 晩冬の季語。 |
| 芋虫 | 蝶の幼虫を指す。 |
| 蛾 | 夏によくみられる蝶に似た外見の虫。 |
蝶の季語を使った俳句
| 俳句 | 作者 |
|---|---|
| 起きよ起きよ 我が友にせん ぬる胡蝶 | 松尾芭蕉 |
| 釣り鐘に とまりて眠る 胡蝶かな | 与謝蕪村 |
| 蝶颯つと 展墓の花を 搏ちにけり | 飯田蛇笏 |
| 蝶々の もの食ふ音の 静かさよ | 高浜虚子 |
| 蝶の舌 ゼンマイに似る 暑さかな | 芥川龍之介 |

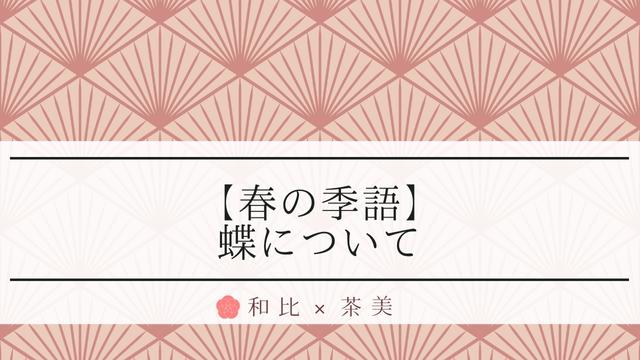
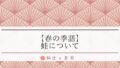

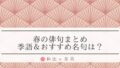


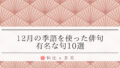



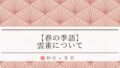

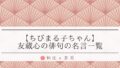

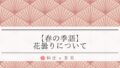
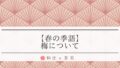
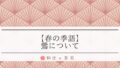

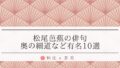




コメント