春はさまざまな鳥たちが活発にさえずりだす季節。
数ある鳴き声の中でも鶯の声は美しく良く響き、人々の心まで春の訪れを届けてくれます。
今回は春を代表する鳥「鶯(うぐいす)」の季語を詳しく紹介します。
鶯の季語はいつ?
| 子季語 | 黄鶯・匂鳥・歌よみ鳥・花見鳥・春告鳥・流鶯 鶯の谷渡り・初音・人来鳥 |
|---|---|
| 関連季語 | 笹鳴・夏鶯・老鶯・晩鶯・残鶯 |
| 時期 | 三春(陰暦の1月~3月) |
| 解説 | 茶緑色の体色ですずめ程の大きさの野鳥。 春を告げる鳥として古来より多くの詩歌に詠まれた。 日本三鳴鳥であり、「ホーホケキョ」と 特徴的な鳴き声でさえずる。 |
鶯の子季語・関連季語を解説
春を告げる鶯には美しい別称が多くあり、子季語となっています。
関連季語には夏・冬の鶯の姿を表す語も。
今にも鶯の可愛らしい鳴き声が聞こえてきそうな語ばかりです。
| 子季語 | 意味 |
|---|---|
| 黄鶯(こうおう) 歌よみ鳥 花見鳥(はなみどり) 人来鳥(ひとくどり) |
鶯の別称。 |
| 経よみ鳥 (きょうよみどり) |
鶯の別称。 鳴き声が「法華経」と聞こえるため。 |
| 春告鳥 (はるつげどり) |
ウグイスの別称。 春の始まりに最も早くさえずるため。 |
| 流燕 (りゅうおう) |
木からきに飛び移りさえずる鶯。 またなめらかにさえずる鶯を指す。 |
| 初音 | 鶯やほととぎすの その年最初の鳴き声を指す。 |
| 鶯の谷渡り | 鶯が鳴きながら、 枝から枝へ飛び渡る情景。 |
| 関連季語 | 意味 |
|---|---|
| 笹鳴 | 三冬の季語。 冬期に鶯が舌打ちするように鳴くこと。 |
| 夏鶯(なつうぐいす) 老鶯(ろうおう) 晩鶯(ばんおう) 残鶯(ざんおう) |
春が過ぎ去った後も鳴き続ける鶯。 |
鶯の季語を使った俳句
| 俳句 | 作者 |
|---|---|
| 鶯や 柳のうしろ 藪の前 | 松尾芭蕉 |
| 流るるは 夕鶯か 橋の下 | 芥川龍之介 |
| 鶯や 朝寝を起こす 人もなし | 正岡子規 |
| 鶯や 人遠ければ 窓に恋ふ | 飯田蛇笏 |
| 鶯の 声遠き日も 暮にけり | 与謝蕪村 |
| 鶯や 文字も知らずに 歌心 | 高浜虚子 |

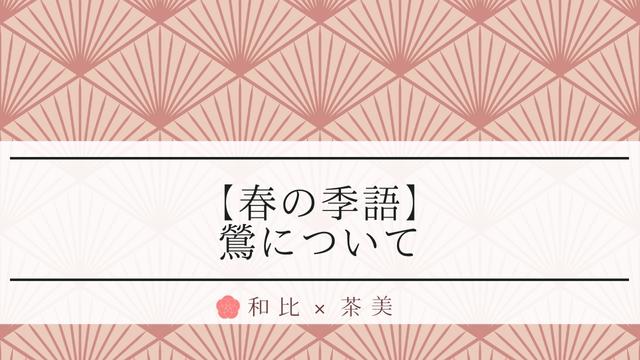

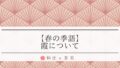
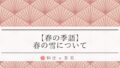

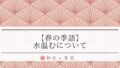

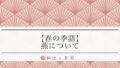
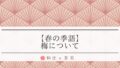

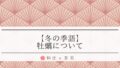

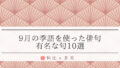
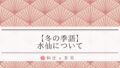
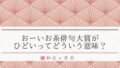


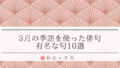
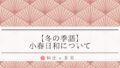




コメント