良く響く美しい鳴き声を持つ雲雀(ひばり)。
春の代名詞とも言われ、麗かな春の情景を表す句に度々登場しています。
今回は季語「雲雀」の季語の意味や有名な俳句例を紹介します。
雲雀の季語はいつ?
| 子季語 | 初雲雀・落雲雀・朝雲雀、夕雲雀、雲雀野・告天使・ 叫天使・初雲雀 揚雲雀・舞雲雀・諸雲雀・友雲雀・ ひめひな鳥・雲雀籠 |
|---|---|
| 時期 | 三春(2月4日から5月6日頃) |
| 解説 | あたたかな陽気の中空を舞ながらさえずり、 春の訪れを告げる鳥。 晴れの日に空高く舞う姿から 「日晴る」と呼ばれたことが、名前の由来。 寒い時期に見られる雲雀は「冬雲雀」といい、 冬の季語となっている。 |
雲雀の子季語を解説
子季語には雲雀の飛ぶ姿や風景を表す語が見られます。
句の雰囲気や情景に合わせて、季語を選んでみましょう。
| 告天使(こくてんし) 叫天使(きょうてんし) ひめひな鳥 |
雲雀の別名称。 |
|---|---|
| 初雲雀 | その年に初めて見られる雲雀。 |
| 揚雲雀(あげひばり) | 鳴きながら空高く舞い揚がる雲雀。 |
| 落雲雀(おちひばり) | 空高く舞い上がりさえずった後、 一直線に降下する雲雀。 |
| 朝雲雀 | 明け方に飛んでいる雲雀。 |
| 夕雲雀 | 夕暮れに飛んでいる雲雀。 |
| 雲雀野 | 雲雀が飛ぶ野の景色。 |
| 舞雲雀 | 空を高く舞う雲雀を指す。 |
| 諸雲雀 | 雄と雌の2匹の雲雀。 |
| 友雲雀 | 群れになっている雲雀。 |
| 雲雀籠 | 雲雀を飼育するための籠。 |
雲雀の季語・子季語を使った俳句
| 俳句 | 作者 |
|---|---|
| 雲雀より 空にやすらふ 峠かな | 松尾芭蕉 |
| 熊谷も 夕日まばゆき 雲雀かな | 与謝蕪村 |
| 山風に ながれて遠き 雲雀かな | 飯田蛇笏 |
| 物草の 太郎の上や 揚雲雀 | 夏目漱石 |
| 夕雲雀 天を貫く 穴や星 | 尾崎紅葉 |
| 何ひとつ 食ふた日もなし 夕雲雀 | 加賀千代女 |

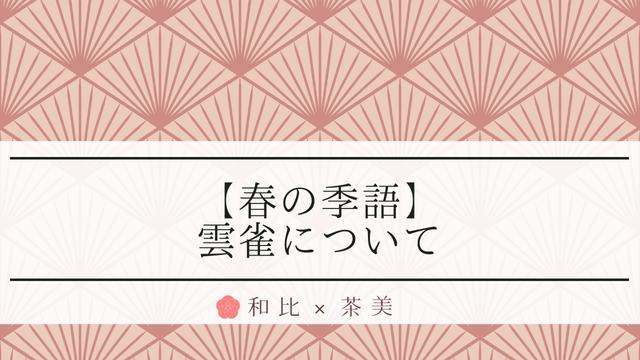

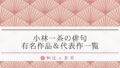

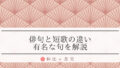
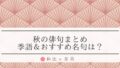

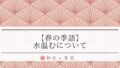

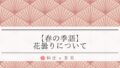
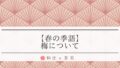
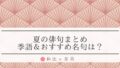


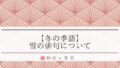
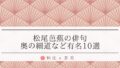
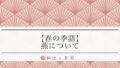

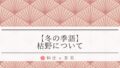




コメント