12月の別称として知られる「師走(しわす)」という語。
実は年末の季語として、たくさんの俳句に登場しています。
今回は季語「師走」を使った有名な俳句や、子季語を紹介します。
▼こちらの記事もおすすめ▼
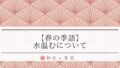
水温むの季語はいつ?仲春?意味や有名な俳句例を紹介
2024.08.212024.08.22
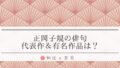
正岡子規の俳句の代表作&有名作品!雑誌「ホトトギス」の中心人物とは
2024.08.212024.08.22
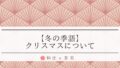
クリスマスの関連季語は?俳句例を紹介
2024.08.212024.08.22

ブランコ・鞦韆の季語はなぜ春?由来は?子季語や意味を紹介
2024.08.212024.08.22
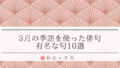
3月の季語を使った俳句|有名な句10例
2024.08.212024.08.22
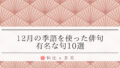
12月の季語を使った俳句|有名な句10例
2024.08.22
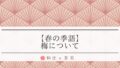
梅の季語はいつ・何月?子季語・関連季語や有名な例句を紹介
2024.08.202024.08.22
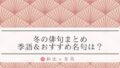
【簡単】冬の季語を使った俳句一覧《小学生・中学生版》
2024.08.202024.08.22
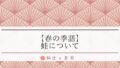
蛙の季語は春・夏どっち?著名な俳人の俳句も紹介
2024.08.202024.08.22

立冬の季語の時期はいつまで?子季語や参考例句も
2024.08.192024.08.22
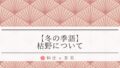
枯野の季語の季節・意味は?俳句や子季語も解説
2024.08.22
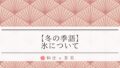
氷の季語を使った俳句|季節は夏・冬どっち?
2024.08.202024.08.22
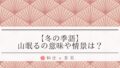
山眠るの季語の意味|どんな情景を表す?時期や子季語は?
2024.08.212024.08.22
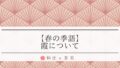
霞の季語を使った俳句は?子季語・関連季語も
2024.08.22
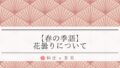
花曇りはどんな情景の季語?子季語や俳句例も紹介
2024.08.22

俳句と川柳の違いは?575の見分け方を解説【例文も紹介】
2024.08.202024.08.22

芥川龍之介の俳句|有名&代表作一覧!飛び石で始まる句は?
2024.08.212024.08.22
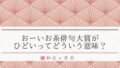
おーいお茶俳句大賞がひどい?コツ&歴代作品の結果例一覧
2024.08.202024.08.22
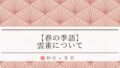
雲雀の季語はいつ?春?それとも冬?俳句の意味や読み方を紹介
2024.08.212024.08.22

大根の季語はいつ?子季語・関連季語や有名俳句も
2024.08.202024.08.22
師走の季語はいつ?
| 子季語 | 極月(ごくげつ)・臘月(ろうげつ) 春待月(はるまちづき)・梅初月(うめはつづき) 三冬月(みふゆづき)・弟月(おとづき) 親子月(おやこづき)・乙子月(おとごづき) |
|---|---|
| 時期 | 12月 |
| 解説 | 12月の別称。年末に師(僧)が忙しく走り回る様子から、 「師走」という漢字があてられた。 |
師走の季語を使った俳句
| 俳句 | 作者 |
|---|---|
| かくれけり 師走の海の かいつぶり | 松尾芭蕉 |
| 旅寝よし 宿は師走の 夕月夜 | 松尾芭蕉 |
| 白足袋の よごれ尽せし 師走哉 | 正岡子規 |
| けろけろと 師走の月夜の 榎哉 | 小林一茶 |
| 炭売に 日のくれかかる 師走哉 | 与謝蕪村 |
| 物ぬひや 夢たたみこむ 師走の夜 | 加賀千代女 |

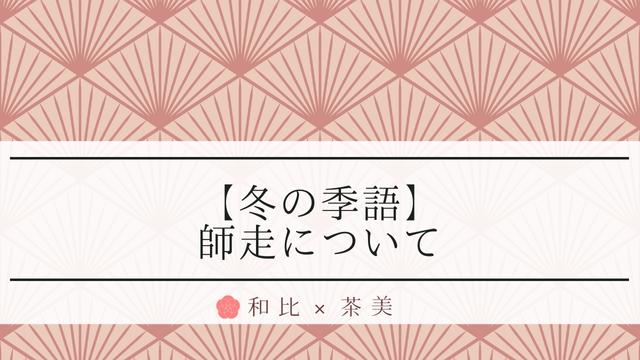

コメント