冬の味覚を代表する牡蠣。
その独特の旨味と栄養価の高さから「海のミルク」とも呼ばれています。
今回は牡蠣は何月の季語なのか、どんな俳句に使用されているのかを紹介します。
牡蠣の季語はいつ?
| 子季語 | 石花・酢牡蠣・どて焼・牡蠣打 |
|---|---|
| 時期 | 三冬(陰暦10月・11月・12月) |
| 解説 | 浅海に生息する二枚貝。 栄養価が高く、実が乳白色であることから 「海のミルク」と別称をもつ。 岩から掻き落とす収穫方法より名づけられたとされる。 |
牡蠣の子季語を解説
子季語には牡蠣の種類や料理を表す語、牡蠣漁をしめす語などがあります。
子季語を知って、牡蠣の味や漁の情景を表してみましょう。
| 子季語 | 解説 |
|---|---|
| 石花 | 牡蠣の別称。 |
| 真牡蠣 | 牡蠣の一種。冬が旬で10月~4月の期間で 水揚げされている。 |
| 牡蠣田 | 牡蠣を養殖する場。 海中に竹や木などを立て並べ、 そこに牡蠣を付着させ育てる。 |
| 牡蠣殻 | 牡蠣の殻。 |
| 牡蠣打 | 牡蠣の実を取り出す作業。 |
| 酢牡蠣 | 牡蠣料理の1つ。牡蠣を酢の物にしたもの。 |
| どて焼 | 牡蠣料理の1つで味噌やみりんで煮込んだもの。 |
牡蠣の季語を使った俳句
| 俳句 | 作者 |
|---|---|
| 牡蠣よりは 海苔をば老の 売りもせで | 松尾芭蕉 |
| 牡蠣をむく 火に鴨川の 嵐かな | 高浜虚子 |
| 牡蠣舟の 薄暗くなり 舟過ぐる | 高浜虚子 |
| 新月を 揺る波に泣く 牡蠣割女 | 飯田蛇笏 |
| 朝比奈も 手負うや 牡蠣の門破 | 尾崎紅葉 |
| 牡蠣舟に 上げ潮暗く 流れけり | 杉田久女 |

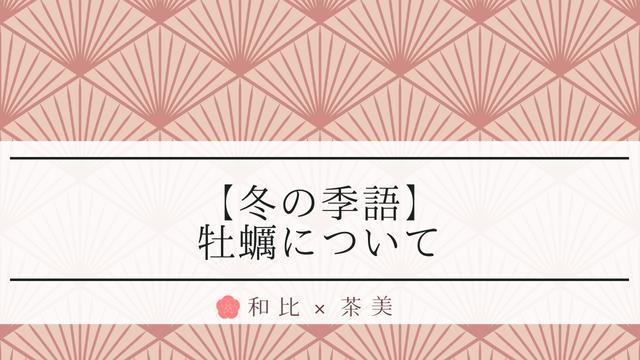
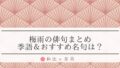
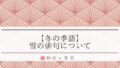
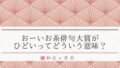

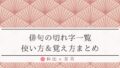

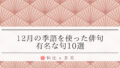
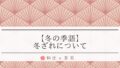
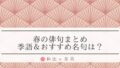

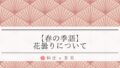

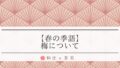


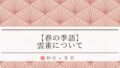
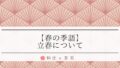

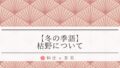
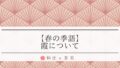


コメント