寒さ厳しい季節の風景に欠かせない「氷」
田んぼや渓谷が氷に包まれる様子は冬にしか見られない光景です。
今回は氷の季語を使った俳句や子季語を詳しく解説しますので、冬の句を詠む際の参考にしてくださいね。
氷の季語はいつ?
| 子季語 | 厚氷・綿氷・蝉氷・氷の声・氷点下・氷塊・氷結ぶ 結氷・氷張る・氷閉づ・氷面鏡・氷雪・氷田 氷壁・氷の楔 |
|---|---|
| 時期 | 晩冬(1月頃) |
| 解説 | 気温が0℃以下になり、水が冷え固まったもの。 |
氷の子季語を解説
氷の子季語には状態を表すものをはじめ、氷が張った田や渓谷の情景など冬ならではの美しい言葉がたくさんあります。
| 子季語 | 解説 |
|---|---|
| 厚氷(あつごおり) | 厚く張った氷。 |
| 綿氷(わたごおり) | 川底に張り付いた綿上の氷。 |
| 蝉氷(せみごおり) | 蝉の羽のような薄さの氷。 |
| 氷塊(ひょうかい) | 氷のかたまり。 |
| 氷点下 | 水が氷に変化する温度。0℃以下。 |
| 氷雪 | 氷と雪を指す。 |
| 氷上 | 氷の上。 |
| 氷の声 | 氷が張るときに生じる音。 |
| 氷の花 | 氷の表面にできた花のような 模様を指す。 |
| 氷張る・氷結ぶ 結氷(けっぴょう)・氷閉づ |
氷が張ること。 |
| 氷面鏡(ひもかがみ) | 氷面が鏡のように物を映す様。 |
| 氷田(ひょうでん) | 氷が張った田んぼ。 |
| 氷壁(ひょうへき) | 寒さ厳しい時期に渓谷が 氷に覆われる様。 |
| 氷の楔(こおりのくさび) | 水が硬く凍てついた様を 楔で閉じたように例えた語。 |
氷の季語を使った俳句
| 俳句 | 作者 |
|---|---|
| あられせば 綱代の氷を 煮て出さん | 松尾芭蕉 |
| 一露も こぼさぬ菊の 氷かな | 松尾芭蕉 |
| あけぼのや 湖の微をとる 氷綱 | 森澄雄 |
| 月陰の砕けては寄る 氷かな | 松笙 |
| 氷漁の 合羽脱げば 乙女なる | 大島民郎 |

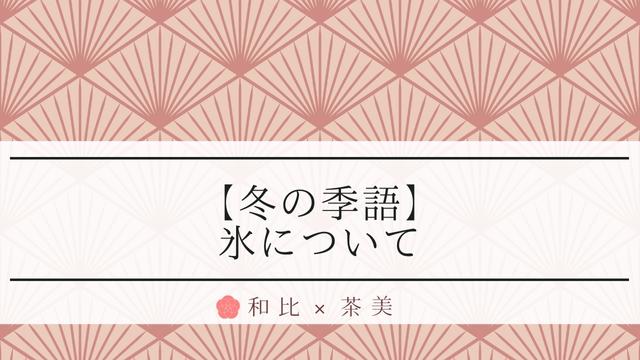
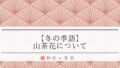

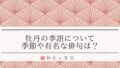
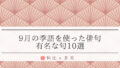

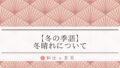
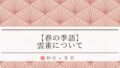
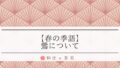

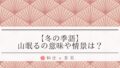

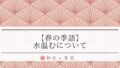
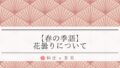

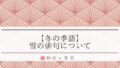

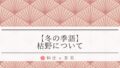
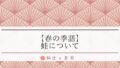




コメント